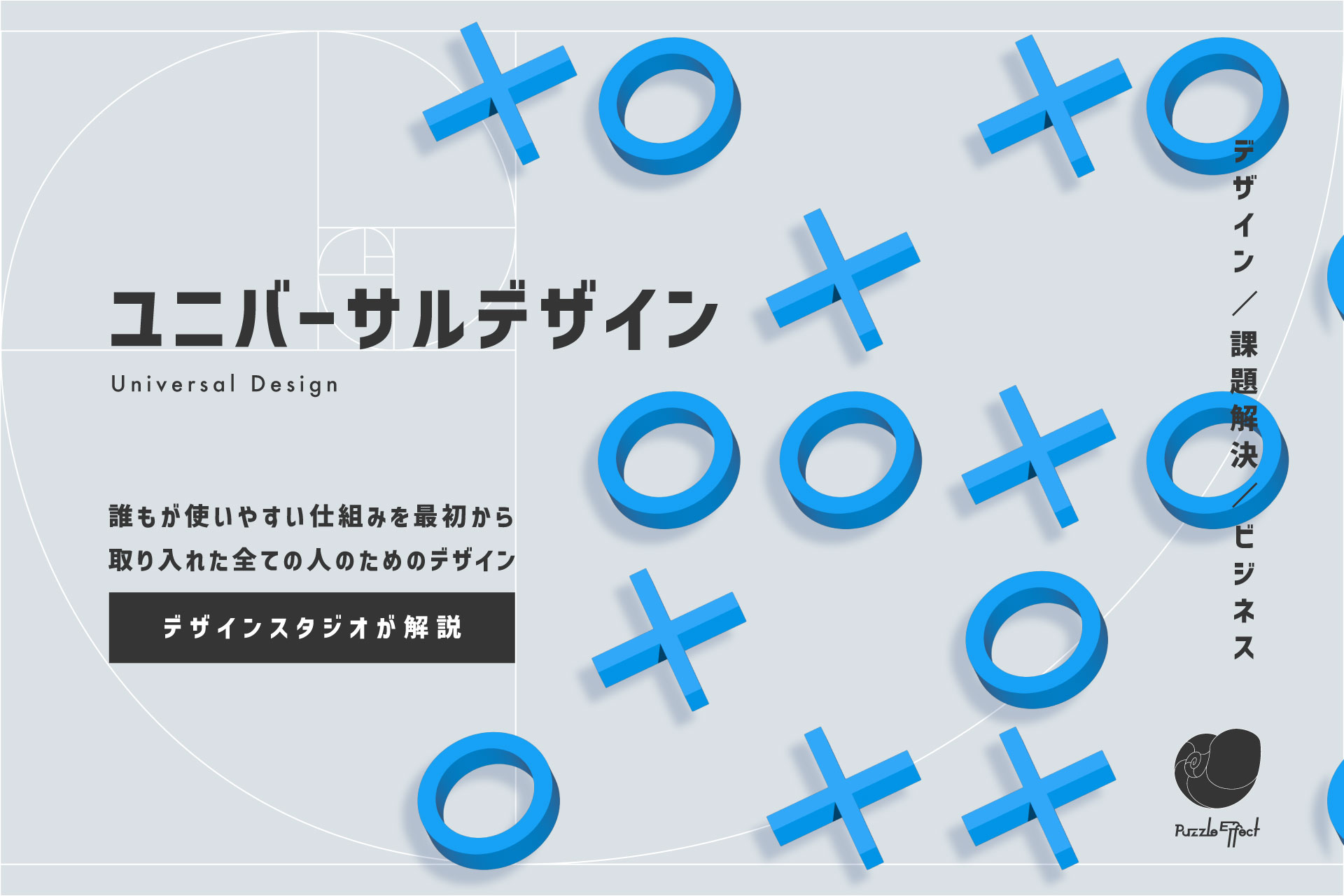ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、身体能力、言語、文化などに関係なく、すべての人が平等に使いやすいように最初から設計されたデザインのことです。これは、特定の人に合わせる「特別な配慮」ではなく、あらゆる人が同じように利用できる「共通の利便性」を追求する考え方です。
ユニバーサルデザインの考え方は、建物や製品、サービス、情報などさまざまな場面に活用されており、自動ドア、エレベーターの音声案内、分かりやすい標識、触って区別できるシャンプーボトルなどが代表的な例です。このような工夫によって、特定の人に限らず、すべての人が不自由なく安全に暮らせる環境が整います。
高齢化や多文化化が進む現代社会において、ユニバーサルデザインはより重要な役割を果たしており、誰もが自分らしく生活できる社会を支える基本的な考え方となっています。今回はユニバーサルデザインについて詳しく解説していきます。
ユニバーサルデザインとは
ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、障害の有無などに関係なく、すべての人が使いやすいように設計されたデザインのことです。特定の人のためだけでなく、できるだけ多くの人にとって使いやすく、わかりやすく、安全であることを目指します。例えば、駅の案内板に使われるピクトグラム(絵文字)や、自動ドア、段差のない歩道、音声案内付きのエレベーターなどは、誰もが利用しやすいよう工夫されたユニバーサルデザインの一例です。
この考え方は、アメリカの建築家ロナルド・メイスによって提唱され、現在では建築、製品、情報、サービスなどさまざまな分野に広がっています。ユニバーサルデザインは「特別な支援を必要とする人」に合わせるだけでなく、「すべての人にとって快適にする」ことを重視しているのが特徴です。少子高齢化が進む現代社会では、ますます重要視されています。
ユニバーサルデザインの目的
ユニバーサルデザインの目的は、どんな人でも「使いやすい」「わかりやすい」「安心できる」ようにすることです。年齢や体の状態、言葉の違いなどに関係なく、すべての人が同じように使えるように、はじめから工夫されたデザインを目指しています。
たとえば、重たいドアの代わりに自動ドアを使えば、力の弱い人や車いすの人、小さな子どもでもスムーズに通れます。また、ボタンの位置や形をわかりやすくすることで、誰でも迷わず操作できます。このように、特別な助けを必要とする人だけでなく、すべての人にとって便利になるのがユニバーサルデザインの良いところです。
目的は、「みんなが同じように暮らしやすい社会をつくること」です。誰かだけががまんしたり、工夫しないと使えないようなものではなく、最初から「みんなのこと」を考えてつくられたものを広げることが大切なのです。
ユニバーサルデザインとバリアフリーとの違い
バリアフリーとユニバーサルデザインは、どちらも「誰もが暮らしやすい社会」を目指す考え方ですが、その目的やアプローチに違いがあります。
バリアフリーとは
バリアフリーは、もともと存在する「障壁(バリア)」を取り除くことを目的としています。高齢者や障害のある人が生活するうえで不便を感じる場所や状況に対して、後から改善・対応する考え方です。例えば、階段にスロープをつける、段差をなくす、手すりを取り付けるなどが典型例です。
ユニバーサルデザインとは
ユニバーサルデザインは、最初から「すべての人が使いやすいように設計する」ことを目指す考え方です。障害の有無、年齢、性別、国籍などにかかわらず、誰もが同じように利用できるようにすることが目的です。自動ドア、音声案内付きエレベーター、多言語対応の標識などが例です。
ユニバーサルデザインとバリアフリーの主な違い
| 項目 | バリアフリー | ユニバーサルデザイン |
|---|---|---|
| 対象 | 主に高齢者や障害者 | すべての人 |
| アプローチ | 後から対応・改善 | 最初から配慮して設計 |
| 例 | 手すりの設置、スロープ追加 | 自動ドア、シンプルな案内板 |
バリアフリーは「ある人の不便をなくす」ことであり、ユニバーサルデザインは「最初からみんなが使いやすいようにする」という違いがあります。
ユニバーサルデザイン7つの原則
ユニバーサルデザインの7つの原則は、誰もが安全・快適に使えるように設計するための基準です。「公平な利用」「柔軟な使い方」「直感的な操作」「情報の認知性」「ミスへの寛容」「少ない負担」「十分な空間」の7つがあり、年齢や障害の有無にかかわらず、多くの人が同じように使える環境づくりを実現します。
1.どんな人でも公平に使えること。
( 公平な利用・Equitable use)
「どんな人でも公平に使えること」は、年齢、性別、能力、障害の有無にかかわらず、すべての人が同じ方法で利用でき、特別な配慮や区別を感じることなく使用できるデザインを指します。利用者が差別や特別扱いを受けることなく、平等にアクセスできることが重要です。
すべての人が同じ体験を共有し、社会的な一体感を高める効果もあります。
例
- 自動ドア 歩行者、車いす利用者、ベビーカーを押す人など、誰もが同じように通行できます。
- 低床バス 乗降時の段差をなくし、高齢者や障害者、子ども連れの人々が安心して利用できる公共交通機関です。
2.使う上での柔軟性があること。
(柔軟な使い方・Flexibility in use)
「使う上での柔軟性があること」は、利用者の多様な好みや能力に対応し、複数の使い方や選択肢を提供するデザインを意味します。右利き・左利きの違いや、身体的特徴、経験の有無など、個々のニーズに応じて使い方を選べることが求められます。
利用者が自分に最適な方法で製品やサービスを使用できるようにし、満足度を高めます。
例
- 高さの異なる手すり 子どもや大人、車いす利用者など、さまざまな身長や体格の人が使いやすいように設置されています。
- 多機能トイレ 障害の有無にかかわらず、誰もが利用できる設備を備えています。
3.使い方が簡単で分かりやすい。
(直感的な操作・Simple and intuitive)
「使い方が簡単で分かりやすい」は、利用者の経験、知識、言語能力、集中力に関係なく、直感的に使い方が理解できるデザインを指します。複雑な操作や学習を必要とせず、誰もが容易に理解し、使用できることが重要です。
誤操作を減らし、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
例
- シャンプーとリンスのボトルの識別 シャンプーボトルには触覚的なマークが付いており、視覚障害者でも触って区別できます。
- 押す部分が大きなスイッチ 直感的に操作でき、高齢者や障害者でも簡単に使用できます。
4.必要な情報がすぐに分かること。
(情報の認知性・Perceptible information)
「必要な情報がすぐに分かること」は、利用者が必要とする情報を効果的に伝達し、環境条件や利用者の感覚能力に関係なく理解できるようにすることを意味します。視覚、聴覚、触覚など、複数の感覚を活用して情報を提供することが求められます。
このようなデザインは、情報の受け取り手が誰であっても、必要な情報を確実に得られるようにします。
例
- 駅の案内表示 視覚的なサインと音声案内を組み合わせ、視覚障害者や聴覚障害者にも情報が伝わるようにしています。
- 色覚異常者向けのカラーユニバーサルデザイン 色の違いが分かりにくい人でも識別できるよう、模様や形状で情報を伝えます。
5.簡単なミスが危険につながらないこと。
(ミスへの寛容・Tolerance for error)
「簡単なミスが危険につながらないこと」は、利用者が誤操作やミスをしても重大な結果や危険が生じないように設計することを指します。エラーマージンを広く取り、事故や損害を未然に防ぐ工夫が求められます。
利用者の安全を確保し、安心して使用できる環境を提供します。
例
- 自動停止機能付きの電動工具 誤って手を離しても自動的に停止し、事故を防ぎます。
- コンセントの安全カバー 子どもが誤って触れても感電しないように保護されています。
6.身体への過度な負担を必要としないこと。
(少ない負担・Low physical effort)
「身体への過度な負担を必要としないこと」は、利用者が無理な姿勢や過度な力を必要とせず、快適に使用できるデザインを意味します。長時間の使用でも疲労が生じにくく、力の弱い人でも問題なく操作できることが重要です。
身体的な負担を軽減するだけでなく、すべての人が長く、快適に製品や環境を使い続けるために必要です。特に、高齢者や障害のある人にとって、少ない力で扱えることは大きな利点となります。また、疲れにくさは誰にとってもありがたく、結果として利用者の幅を広げ、満足度の向上にもつながります。
例
- レバー式のドアノブ ひねる動作が難しい人でも、押す・引くだけで簡単に開けられます。
- 軽い力で操作できる蛇口やリモコン 関節に負担がかかりにくく、高齢者や筋力の弱い人でも無理なく使えます。
7.利用のための十分な大きさと空間が確保されていること。
( 十分な空間・Size and space for approach and use)
「利用のための十分な大きさと空間が確保されていること」は、利用者が安全かつ快適に製品や設備に近づき、操作できるよう、適切な広さや配置を確保することを意味します。身体のサイズや動きの違い、使用する道具(例:車いす、杖、ベビーカー)に対応できる空間づくりが求められます。
「届かない」「通れない」「見えない」といった利用者の不便を防ぎ、多様な人々にとって快適で安全な環境を実現します。
例
- 車いす対応のトイレやエレベーター 十分な回転スペースと移動経路が確保されています。
- 自動販売機のボタンや画面が子どもや車いす利用者の目線にも合わせて設計されている 立ったままでも座ったままでも操作可能です。
身近なユニバーサルデザイン
身近なユニバーサルデザインは、私たちの日常の中に多く取り入れられています。たとえば、駅の自動改札機は、ICカードをかざすだけで通れるように設計されており、小さな子どもから高齢者まで簡単に使えます。また、エレベーターには点字ボタンや音声案内があり、視覚や聴覚に不安がある人にも配慮されています。
ペットボトルのキャップにある開けやすい溝や、シャンプーとリンスを見分けるためのボトルのギザギザも、誰でも間違えずに使えるように工夫されたデザインです。さらに、横断歩道の音響信号機は、視覚に障害のある方が安心して道路を渡れるようサポートしています。
スマートフォンの設定で文字サイズや色合いを変更できる機能も、多様な利用者に対応するためのユニバーサルデザインの一例です。このように、身近な場所や製品にある細やかな配慮が、多くの人の生活をより快適にし、すべての人が安心して使える社会を支えています。
UDフォント
UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)とは、誰にとっても読みやすく、誤読しにくいように設計された書体のことです。特に、高齢者や視覚に不安のある人、ディスレクシア(読み書き障害)のある人、日本語を学ぶ外国人など、幅広い人が文字を正確に、スムーズに読めるように工夫されています。
UDフォントは単に「見やすい」だけでなく、「すべての人に伝わる文字」を目指して設計されたフォントです。社会全体で情報の格差を減らし、誰もが安心して生活できる環境をつくる一助となっています。興味があれば実際にUDフォントを比較してみるのもおすすめです。
よく使われているUDフォントの例
- UD新ゴ(モリサワ)
- BIZ UDゴシック / BIZ UD明朝(マイクロソフト提供)
- イワタUDフォント
ピクトグラム
ピクトグラムとは、言葉を使わずに、絵や記号で意味を伝える図記号のことです。誰にでもわかりやすく情報を伝えるために使われており、言語や文化、年齢に関係なく理解されやすいのが特徴です。現在のピクトグラムが本格的に登場したのは、20世紀の国際イベントや公共交通機関の整備とともにです。1964年 東京オリンピックでは、日本語が通じない外国人観光客に配慮し、競技種目を表す統一されたピクトグラムが初めて導入されました。その後、1972年のミュンヘンオリンピックでは、デザイナーのオトル・アイヒャーがより体系的なピクトグラムを開発。これが世界中の公共サインの基準となり、多くの国で採用されました。
国際的には、ISO(国際標準化機構)によって安全標識や公共案内のピクトグラムが統一され、言語を問わず誰にでも伝わるようデザインされています。
ピクトグラムは、視覚情報として瞬時に内容を伝えることができるため、言葉に頼らず誰にでも「伝わる」デザインとして、ユニバーサルデザインの中でも重要な役割を担っています。
今後も国際化・高齢化・多様化が進む社会において、多くの人に配慮した情報伝達の手段としてその活用が期待されています。
- トイレの男女マーク
- 非常口の走る人のマーク
- 禁煙・火気厳禁のマーク
- 駐車場やエレベーターの表示
まとめ
ユニバーサルデザインは、ただ便利であるだけでなく、すべての人にとって「使いやすさ」や「分かりやすさ」「安全性」を提供するための大切な考え方です。社会には、身体的・感覚的な違いを持つ多くの人々が生活しており、そうした人たちを含めた全員が快適に過ごせるよう、初めから配慮された設計が求められています。
これは特定の人への支援ではなく、結果としてすべての人にとっての利便性向上にもつながります。たとえば、誰でも簡単に操作できる装置や、情報を多様な方法で伝える表示などは、日常生活のストレスを減らし、安心感をもたらします。
Puzzle Effectでもユニバーサルデザインを制作しています。
今後ますます多様化が進む社会において、ユニバーサルデザインの視点を持つことは、私たち一人ひとりにとって重要です。身近なところからその考えを取り入れ、誰にとってもやさしい社会づくりを進めていきましょう。