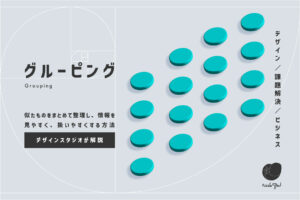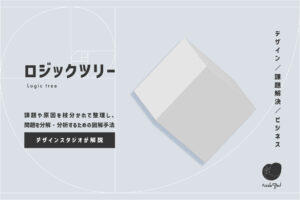「ユーザーは他のサイトと同じように動作することを期待している」それがヤコブの法則です。
独自性ばかりを追いかけるのではなく、ユーザーが慣れ親しんだデザインを取り入れることが、快適な体験を生む近道になります。
本記事では、WebやアプリのUI/UX設計でよく使われるこの法則について、基本の考え方から具体例、実際の使い方までをわかりやすく解説します。
ヤコブの法則とは
ヤコブの法則(Jakob’s Law)とは、「ユーザーは他のサイトで得た経験に基づいて、あなたのサイトも操作しようとする」というユーザー行動の法則です。
つまり、Webサイトやアプリを設計する際には、ユーザーがすでに慣れている操作感やデザインパターンを尊重することが大切だという考えです。斬新さを追求しても、慣れ親しんだレイアウトや動線が崩れていると、ユーザーは混乱し、離脱してしまう可能性があります。だからこそ、ユーザーが他のサービスで学習した操作性を活かすことで、違和感なく快適に使ってもらえるのです。ヤコブの法則は、ユーザー中心設計の基本であり、特にUI/UX設計において重要な前提とされています。
代表的な例
ヤコブの法則が活かされている例として、ECサイトのカート機能があります。多くのサイトでは、画面右上に「カート」アイコンが配置されており、商品追加後もそこで確認できる仕様が共通です。
新しいECサイトでもその配置を踏襲することで、ユーザーは戸惑うことなく操作できます。もし独自性を優先して、左下にカートを置くなどした場合、ユーザーは混乱し、使いづらいと感じる可能性が高まります。このように、慣れたパターンに沿うことでユーザー体験が向上します。
ヤコブ・ニールセンとは
ヤコブ・ニールセン(Jakob Nielsen)は、ユーザビリティ分野の第一人者として知られるデンマーク出身のコンピュータ科学者です。元はAppleやSun Microsystemsでも活動しており、1998年にはドナルド・ノーマンとともに「ニールセン・ノーマングループ(NN/g)」を設立。
彼の提唱する「10のユーザビリティヒューリスティックス」は、今もUI/UX設計の基準として広く使われています。ヤコブの法則も彼の経験と研究から導かれた重要な知見です。
ヤコブの法則を使うには
ヤコブの法則を活用するには、「ユーザーがどんな体験に慣れているか」を知り、それに合わせた設計を行うことが基本です。UIや導線、ボタン配置などで奇をてらうよりも、他の主要サービスと共通する設計を採用することで、ユーザーは違和感なく操作できます。
そのためには事前のリサーチや慣習の理解が重要です。また、すべてを決め打ちせず、実際のユーザーの反応を確かめるA/Bテストを繰り返すことで、最適な構成に近づけていくことが可能です。新しさと使いやすさのバランスを見極めることが、ヤコブの法則を活かす設計の鍵です。
リサーチ
ヤコブの法則を活かす第一歩は、ユーザーが普段どんなサイトやアプリを使っているかを調査することです。たとえば、自社サイトのターゲット層が頻繁に利用している他サービスのUIを観察し、共通するボタン配置や用語、導線を把握することが大切です。ユーザーが既に持っている「こう動くだろう」という期待値を知れば、設計時にそれを裏切らない構成がしやすくなります。リサーチはユーザーとのズレをなくすための基礎です。
慣習優先
UI設計においては、独自性よりも「慣れている操作感」を優先することが、ヤコブの法則に基づく設計の基本です。
たとえば、検索ボックスは右上に、ハンバーガーメニューは左上に、というように多くのサイトが採用している慣習は、ユーザーが自然と操作できる“暗黙のルール”です。それを無視して独自の配置にすると、使いにくさや混乱の原因になります。新しさは、あくまで“ユーザーが迷わない範囲”で取り入れるべきです。
A/Bテスト
ユーザーが慣れている設計を推測しても、それが本当に使いやすいかは検証しなければわかりません。そこで有効なのがA/Bテストです。2つ以上のUIパターンを実際に使ってもらい、クリック率や離脱率などの数値で比較することで、どの設計がより直感的で使いやすいかが明確になります。
ヤコブの法則は“経験則”ですが、最終的には実データをもとに改善していくことが、確かなユーザー体験を生む鍵となります。
メンタルモデル
メンタルモデルとは、ユーザーが「こうすればこう動くはず」と頭の中に持っている、物事の理解や操作のイメージのことです。たとえば、パソコンの「ごみ箱」やスマホの「スワイプで削除」は、実生活の経験から連想されるモデルを反映しています。UI/UX設計では、ユーザーのメンタルモデルに合った操作性や表現を採用することで、説明なしでも直感的に理解・行動できる仕組みがつくれます。
メンタルモデルの具体例
たとえば、メールアプリで「紙飛行機のアイコン=送信」だと認識できるのは、ユーザーが“飛ばす=届ける”という経験に基づいたメンタルモデルを持っているからです。
また、ECサイトでカートのアイコンが買い物かごの形をしているのも、実際の買い物の経験に基づいた連想を活かしています。このように、現実世界の行動や道具と一致するデザインは、ユーザーが迷わず操作できる直感的なUIにつながります。
まとめ
ヤコブの法則は、ユーザーの「慣れ」を尊重することの大切さを教えてくれます。使い慣れた構造や表現を活かすことで、ユーザーは迷わず操作でき、サービスへの満足度も向上します。
独創的なアイデアを活かすためにも、まずは「違和感のない設計」をベースにすることが重要です。ヤコブの法則を理解し、活用することで、誰にとっても使いやすいUIを実現しましょう。