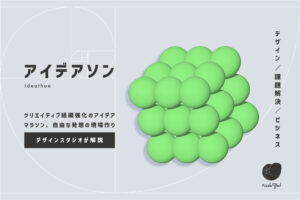「楽しさ」で人を動かす仕掛け──それがファン・セオリー(Fun Theory)です。義務や罰ではなく、好奇心や遊び心によって人々の行動を自然に変えるこの考え方は、公共マナーや健康促進など多くの場面で活用されています。
本記事では、ファン・セオリーの意味や背景、代表的な事例、応用のためのゲーミフィケーション手法、そして活用する際の注意点までをわかりやすく解説します。楽しさがもたらす行動変容の可能性を知りたい方におすすめの内容です。
楽しさで人を行動させる『ファン・セオリー』とは?
ファン・セオリー(Fun Theory)とは、「人は義務感や罰ではなく、“楽しさ”によって行動を変える」という考え方です。スウェーデンのフォルクスワーゲン社が提唱し、公共の場でのマナー改善や健康習慣の促進などに応用されてきました。たとえば階段をピアノの鍵盤のようにして音が鳴る仕掛けを加えると、普段エスカレーターを使う人でも階段を選ぶようになるなど、楽しい体験によって行動変容が自然に引き起こされます。
めんどくさいを回避する楽しい選択肢
人は基本的に「面倒なこと」を避けたいと感じますが、そこに“楽しさ”を加えることで、自然と行動が変わることがあります。たとえば、ゴミ箱に投げ入れると面白い音が鳴る仕掛けをつければ、ポイ捨てせずにゴミを捨てたくなります。このように、義務やルールだけでは行動が促せない場面でも、楽しさという要素を取り入れることで、自発的かつ継続的な行動を引き出すことができるのがファン・セオリーの強みです。
ファン・セオリーの実例
ファン・セオリーは実際にさまざまな公共空間で活用され、成功を収めています。中でも注目されたのが「世界で最も深いゴミ箱」や「ピアノ階段」といった仕掛けです。これらは一見すると単なる遊びのように見えますが、人々の行動を自発的に変える大きな力を持っていました。面倒・退屈とされる行動に、ちょっとした驚きや楽しさを加えるだけで、習慣やマナーを改善できることを証明しています。
世界で最も深いゴミ箱
ストックホルムの公園に設置された「世界で最も深いゴミ箱」は、ゴミを入れると“ヒューン…”という長い落下音が鳴るユニークな仕掛けが施されていました。この仕掛けにより、多くの人が興味本位でゴミを捨てるようになり、周囲の清掃状況が大幅に改善されました。楽しさが動機となる好例です。
ピアノ階段
駅の階段を大きなピアノの鍵盤に見立てて、一段ごとに音が鳴るようにした「ピアノ階段」は、ファン・セオリーの代表的な事例です。エスカレーターより階段を使う人の割合が66%も増加し、健康促進や行動変容の効果が確認されました。楽しい体験が、人々を自然に行動させる力を持っていることを示しています。
フォルクスワーゲン社でファン・セオリーが生まれた背景
フォルクスワーゲン社でファン・セオリー(Fun Theory)が生まれた背景には、「人々の行動をより良く変えるにはどうすればよいか」という社会的な問題意識があります。同社は2009年、環境負荷の少ない車や技術を開発するだけでなく、人々のライフスタイル自体を前向きに変えていくことが重要だと考えました。そこで着目したのが「楽しさ」の力です。罰や強制による行動変容ではなく、楽しさや好奇心が人の行動を自然に変えるのではないか、という仮説のもとにプロジェクトがスタートしました。
この試みは「The Fun Theory」というキャンペーンとして展開され、スウェーデンの公共スペースを舞台にさまざまな実験が行われました。ピアノ階段や深いゴミ箱など、誰もが参加できるシンプルかつユーモラスな仕掛けが、実際に人々の行動を変えることに成功。フォルクスワーゲンはこのプロジェクトを通じて、「楽しいことが世界を変える」という新たな価値観を提案しました。
ファン・セオリーを実現させるゲーミフィケーションとは?
ファン・セオリーを現実の仕組みに応用するうえで重要なのが「ゲーミフィケーション」です。これは、ゲームの要素や仕組みを日常の行動やサービスに取り入れ、人々のやる気や行動を引き出す手法です。義務的・面倒に感じる行動も、ゲームのように楽しく設計すれば自発的に取り組めるようになります。ファン・セオリーと同様、行動変容を促すために「目的」「達成感」「報酬」「可視化」などが重要な要素になります。
目的
ゲーミフィケーションではまず、参加者にとって意味のある「目的」を明確にすることが重要です。何のためにその行動をするのかが明確になれば、動機づけが自然に生まれます。健康のために階段を使う、環境のためにゴミを捨てるなど、行動の先にある意義を伝えることで、楽しい仕組みに納得して参加してもらいやすくなります。
クエスト
クエストとは、ゲームにおける「やるべき課題」や「ミッション」のことです。ゲーミフィケーションでは、現実の行動を小さなタスクに分け、段階的にクリアしていく形にすると、達成感を感じながら継続しやすくなります。たとえば、「今日は階段を3回使う」など、明確で達成可能な目標を提示することで、楽しみながら行動を積み重ねられるようになります。
報酬
報酬は、行動の達成によって得られるごほうびで、モチベーション維持に大きな効果があります。ポイントやバッジ、称号、ランキングなど、目に見える報酬は行動への期待感を生み出します。物理的な景品がなくても、「褒められる」「見える化される」といった心理的な報酬でも十分に効果があります。楽しい体験がそのまま報酬になることもあります。
可視化
可視化とは、自分の進捗や成果がひと目で分かるようにする仕組みです。カウントアップ、グラフ、レベル表示など、現在の状況を視覚的に見えるようにすると、やる気の維持につながります。人は変化や成長を確認できると、さらに取り組みたくなる心理が働くため、ゲームの進行状況のように行動結果をフィードバックすることが重要です。
ファンセオリーの欠点・注意点
ファン・セオリーは「楽しさ」で人を動かす有効な方法ですが、いくつかの欠点や注意点もあります。最大の課題は継続性の弱さです。一時的に注目や行動を引き出すことはできても、「楽しいからやる」という動機は習慣化につながりにくく、飽きられると元に戻ってしまう可能性があります。
また、仕掛けが過剰だと本来の目的が見失われたり、コストに見合わなかったりする点も問題です。導入の際は、「一時的な演出」で終わらせず、目的との一貫性を持たせること、そして行動の習慣化へつながる工夫が求められます。仕組み自体をアップデートし続ける意識も大切です。
まとめ
ファン・セオリーは、人の行動を「強制」ではなく「自発的な楽しさ」によって変えるという発想から生まれました。ピアノ階段や深いゴミ箱のような事例は、楽しさが人々の行動に大きな影響を与えることを示しています。
ただし、継続性や目的との整合性を保つ工夫がなければ、単なる一時的な娯楽で終わってしまいます。行動をよりよい方向へ導くためには、「楽しい仕掛け」に意味と持続力を持たせることが重要です。あなたの身の回りでも、楽しさを取り入れた工夫を考えてみませんか?
Puzzle Effectはこのファンセオリーの活動にとても感動し積極的に体験を楽しくする仕組みやプロダクトの開発を行なっています。また継続性や目的意識を重要視したディレクションを行なっています。”体験”を重要視したデザインやものづくりやシステム作りのご相談・ご連絡をお待ちしております。