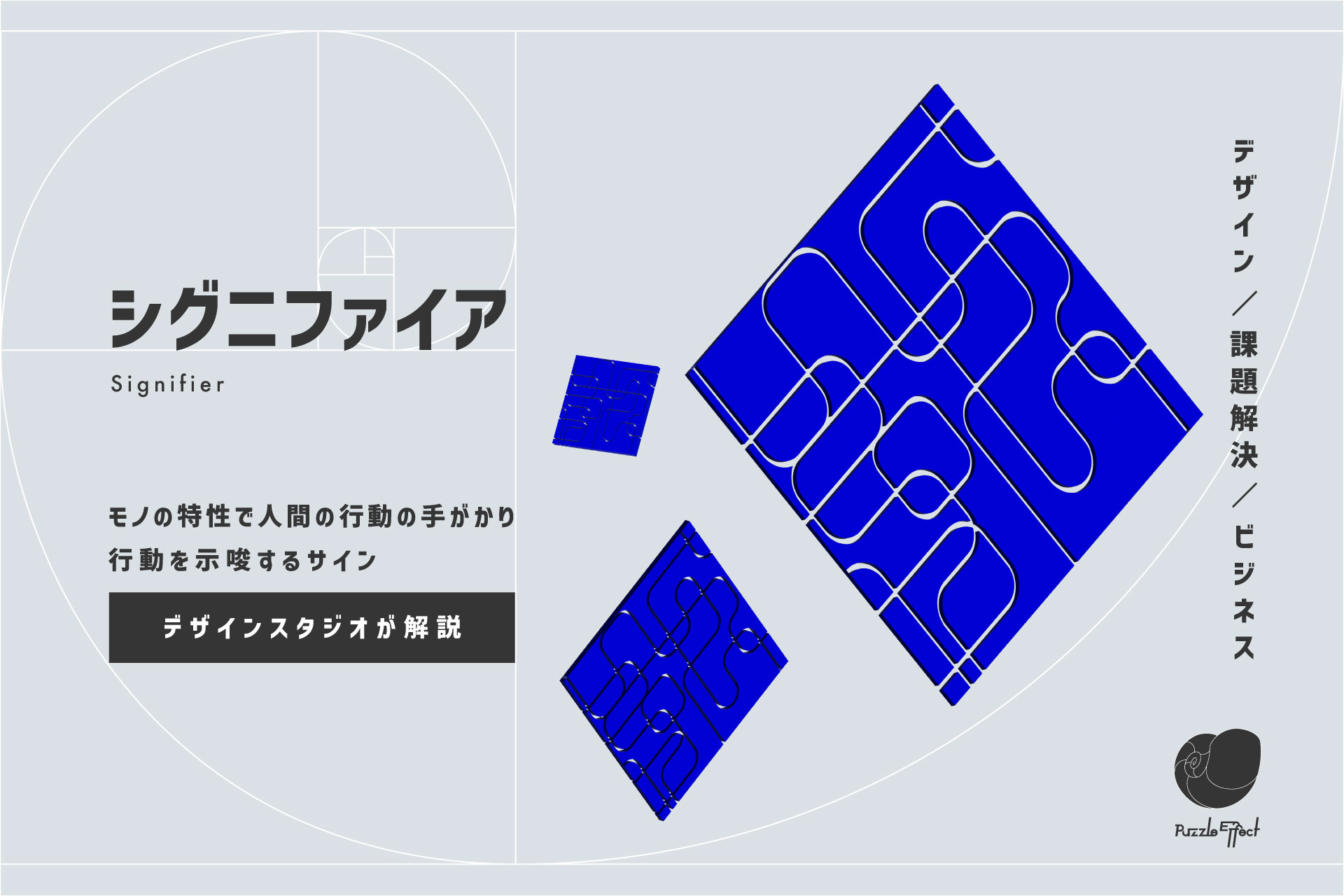シグニファイアとは、物や画面の中で「どのように操作すればよいか」「どんな行動を取るべきか」を人に視覚的・物理的・音響的に伝える手がかりのことです。ドアの取っ手やクリック可能なリンク、スマホの通知バッジなどがその例で、ユーザーが直感的に動けるよう導く役割があります。ドナルド・ノーマンが提唱し、UI/UXやプロダクトデザイン、建築、教育現場など多岐にわたる分野で重視されています。今回はシグニファイアにクローズアップして詳しく解説していきます。
シグニファイアとは
シグニファイアとは、ユーザーがある対象物をどのように操作すればよいかを示す手がかりことです。たとえば、ドアの取っ手は「ここを引く」とユーザーに行動を促す視覚的なサインとなります。これは心理学や人間工学の分野で使われる概念で、プロダクトデザインやユーザーインターフェース設計などにおいて重要な要素です。
シグニファイアが適切に設計されていれば、ユーザーは迷うことなく直感的に行動を起こせます。逆にシグニファイアが曖昧だったり不在だったりすると、ユーザーは誤った操作をしてしまう可能性があります。
人と物との間に生まれる行動・行為
人と物との関係は、物に備わっている機能だけではなく、それにどのようなシグニファイアがあるかによって大きく左右されます。たとえば、椅子は「座るためのもの」としての機能を持っていますが、座面が傾いていたり座るところが特殊な形だと、「ここに座っていいのか?」という迷いが生じます。
このように、物の形状・配置・質感といった視覚や触覚に訴える要素が、私たちの行動を引き出すのです。つまり、物が発するシグナルを人が読み取り、それに応じて行動が起こるという相互関係が存在します。この関係性こそが、日常の中で私たちが自然と行っている「人と物とのやりとり」と言えるでしょう。
シグニファイアの意味
シグニファイアとは、人がある物事や環境に対してどのように関わればよいかを示す「手がかり」や「合図」のことを指します。もともとは記号論や言語学で用いられた言葉ですが、現在では心理学やデザイン、ユーザーインターフェースの分野でも広く使われています。
たとえば、エレベーターのボタンに矢印が描かれていれば「上に行く」「下に行く」という意味が直感的に理解できるように、行動を導くヒントとなる要素がシグニファイアです。人は無意識のうちにシグニファイアを読み取り、それに基づいて行動を選択します。そのため、シグニファイアの存在はスムーズなコミュニケーションや使いやすい設計に欠かせない要素となっています。
心理学上のシグニファイア
心理学におけるシグニファイアは、人間が環境から受け取る刺激を手がかりに行動を決定するプロセスを説明する際に用いられます。人は物や状況から「意味のあるサイン」を見つけ、それに応じて適切な反応をとる傾向があります。
たとえば、赤信号は「止まるべきだ」という合図として捉えられ、反射的に立ち止まるという行動が生まれます。このように、外部環境にある情報が、内的な認知や意思決定のトリガーとなることが多く、これは「知覚のシグニファイア」と呼ばれることもあります。心理学上のシグニファイアは、環境との相互作用を通じて人がどのように意味を解釈し、行動を選択するかを理解するうえで重要な概念です。
デザイン上のシグニファイア
デザインにおけるシグニファイアとは、ユーザーに「どのように操作すればよいか」「どのように使えばよいか」を直感的に伝える視覚的・物理的な手がかりです。たとえば、ボタンが立体的に見えるデザインになっていれば、「ここを押せばよい」とユーザーは理解しやすくなります。
ドアノブ、スライダー、スクロールバーなど、あらゆるユーザーインターフェースにおいてシグニファイアは重要な役割を果たしています。ドナルド・ノーマンは著書『誰のためのデザイン?』の中で、良いデザインとはユーザーが迷わず使えるようにシグニファイアをうまく取り入れたものであると述べています。使いやすい製品やサービスを作るためには、見た目・形・動き・音といったさまざまな表現方法で、ユーザーに適切な情報を届けることが不可欠です。
シグニファイアの体験設計
体験設計においてシグニファイアは、ユーザーがサービスや製品に触れたときに、スムーズかつ迷いなく目的を達成できるよう導く役割を果たします。良い体験設計とは、ユーザーの行動を無理なく誘導し、ストレスを感じさせないことです。
たとえば、ショッピングサイトにおける「カートに入れる」ボタンの配置や色、アイコンは、ユーザーが次にとるべき行動を明確に示します。これらの要素が視覚的・機能的に整理されていると、ユーザーは意図した行動を自然に行うことができ、満足度の高い体験へとつながります。つまり、シグニファイアは単なる装飾ではなく、体験そのものを設計する基盤として位置づけられます。
シグニファイアの効果
シグニファイアには、ユーザーの認知負荷を軽減し、操作や判断をスムーズにする効果があります。たとえば、押せそうな見た目のボタン、引くべき方向を示す取っ手の形などは、言葉による説明がなくてもユーザーに行動の選択肢を示します。
このように、シグニファイアは直感的な理解を促すことで、無駄な試行錯誤を減らし、使い勝手の良さを向上させます。特に高齢者や子どもといった多様なユーザー層がいる場面では、シグニファイアの明瞭さがユーザビリティの鍵を握ります。また、エラーの発生を防ぐ効果もあり、安心感や信頼感を与えることにもつながります。これにより、ユーザーは製品やサービスに対して良好な印象を持ちやすくなります。
メンタルモデルからシグニファイアを作る
メンタルモデルとは、ユーザーが頭の中で描いている「仕組みや操作に関する予想や理解」のことです。シグニファイアを設計する際には、このメンタルモデルに寄り添った表現が非常に重要になります。
たとえば、多くの人が「右に回すと開く」「ゴミ箱は削除」といった共通認識を持っています。これに反するデザインがあれば、ユーザーは戸惑い、誤操作をする可能性があります。そこで、ユーザーのメンタルモデルに合わせてシグニファイアを設計すれば、自然で直感的な操作が可能になります。つまり、ユーザーの思考と行動のギャップを埋めるために、シグニファイアはその橋渡しとして機能するのです。このような設計姿勢がUXの質を左右します。
シグニファイアのUXデザイン
UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインにおいてシグニファイアは、ユーザーが製品やサービスを「どう使うか」を示す核心的な要素です。たとえば、スマホアプリのアイコンが動きや色で反応を示せば、ユーザーはどのような操作が可能かを瞬時に把握できます。シグニファイアが適切に設計されていれば、ユーザーは迷うことなく次のステップに進むことができ、快適な体験を得られます。
逆に、シグニファイアが不明確だと、操作に対する不安やストレスが生じ、離脱の原因になります。UXデザインの本質は、ユーザーの行動と感情に寄り添い、期待と実際の使用体験を一致させることです。そのため、わかりやすく自然なシグニファイアは、ユーザー体験における超重要要素です。
シグニファイアの歴史
シグニファイアという概念は、もともと言語学や記号論の分野で使用されていた用語です。
特にフェルディナン・ド・ソシュールは、言葉が「シニフィアン(記号表現)」と「シニフィエ(記号内容)」の関係によって成り立っているとし、その中で「シニフィアン」は対象を指し示す要素、つまりシグニファイアとして理解されてきました。
この記号論的な概念がデザイン分野に応用されたのは、認知心理学者であるドナルド・ノーマンによる影響が大きいです。彼は1988年に出版した著書『The Design of Everyday Things(邦題:誰のためのデザイン?)』の中で、当初「アフォーダンス(affordance)」という用語を用いて、物の形状が人にどのような行動を促すかを説明していました。しかし後にこの概念が誤解されやすいと判断し、「シグニファイア」という言葉を改めて導入します。これにより、「行動を促すための明示的な手がかり」という意味でのシグニファイアが、デザイン理論の中で広く認知されるようになりました。今日では、UI/UX設計、工業デザイン、建築、教育分野など、さまざまな領域で重要な設計要素として位置づけられています。
『何のためのデザイン』で書かれたシグニファイア
『誰のためのデザイン?』の中でドナルド・ノーマンは、当初「アフォーダンス」という言葉を中心に論じていましたが、その後、より明確に行動のヒントとなる要素を説明するために「シグニファイア」という概念を導入しました。ノーマンによれば、アフォーダンスは物が持つ潜在的な機能であり、シグニファイアは「その使い方を示す手がかり」です。たとえば、ドアに引きやすい取っ手があれば、それは「ここを引いてください」と視覚的に教えてくれるシグニファイアになります。このように、ユーザーが直感的に正しい操作を選べるようにするためには、視覚的・触覚的にわかりやすいシグニファイアの設計が不可欠であると述べられています。ノーマンのこの理論は、デザインの実務者だけでなく、教育や公共施設の設計などにも応用されており、広く影響を与えています。
アフォーダンスとの違い
シグニファイアとアフォーダンスは、どちらも人の行動に影響を与えるデザイン要素ですが、役割と意味は異なります。アフォーダンスは「物が本来的に持つ使い方の可能性」であり、シグニファイアは「その使い方を人に伝える手がかり」です。
たとえば、マグカップの持ち手は「手でつかめる」というアフォーダンスを持ちますが、その持ち手が明確に見える形状であれば「ここを持ってください」というシグニファイアになります。つまり、アフォーダンスは物理的・機能的な特徴を指し、シグニファイアはユーザーにその特徴を“気づかせる”ための情報です。この違いを理解することで、ユーザーが誤解せずに正しく製品を使えるような設計が可能になります。
アフォーダンスとは
アフォーダンスとは、ジェームズ・J・ギブソンという心理学者が提唱した概念で、「環境が生物に対して与える行動の可能性」を意味します。物体の形や素材、配置が自然と行動を促すことを指し、たとえば椅子は「座ることができる」、ボタンは「押すことができる」といったように、人がその機能を理解せずとも感じ取れるものです。
アフォーダンスは必ずしも見た目でわかる必要はなく、機能そのものに内在していることが特徴です。そのため、アフォーダンスは潜在的な可能性を示す一方で、ユーザーが気づかなければ活用されないこともあります。
アフォーダンスのデザイン
アフォーダンスのデザインとは、物や環境の持つ「行動の可能性」を、自然な形でユーザーに感じさせる設計手法です。たとえば、ドアの形が押しやすいように平らになっていれば「押す」行動を誘導できますし、椅子が腰をかけやすい高さと形状であれば「座る」動作が自然と起こります。
このように、アフォーダンスを活かしたデザインは、ユーザーに意識させずとも適切な行動を導くことができます。ただし、アフォーダンスが存在していても、それがユーザーにとって明確でなければ意味を持ちません。そこで視覚的な手がかりとしてシグニファイアを組み合わせることで、アフォーダンスを効果的に伝えることが可能になります。アフォーダンスとシグニファイアは相互に補完し合うことで、より使いやすいデザインへとつながります。
シグニファイアの例
こうしたシグニファイアは、説明がなくても「どうすればいいか」が伝わるよう設計されています。特にデザインやUI/UXの分野では、ユーザーに意図した行動を自然に取らせるための重要な要素として直感のデザインとして重視されています。
| シーン | シグニファイアの例 | 伝えていること(行動) |
|---|---|---|
| ドア | 取っ手やプッシュプレート | 引く、押す |
| エレベーター | 上下の矢印ボタン | 上に行く、下に行く |
| Webサイト | 青く下線のついた文字リンク | クリックできる |
| アプリのUI | ゴミ箱アイコン | 削除する |
| テキスト入力欄 | 点滅するカーソル | ここに入力できる |
| 駅の案内標識 | ピクトグラム(例:トイレマーク) | 施設の場所を案内する |
| テレビのリモコン | 凹凸のある電源ボタン | 押せる、電源の操作 |
| 自動販売機 | 点灯した購入ボタン | 購入可能状態である |
| スマホの通知バッジ | 赤い丸や数字の表示 | 新しい情報がある |
まとめ
シグニファイアは、ユーザーの行動を明確にし、操作ミスを減らし、製品やサービスとの良好な関係を築くための重要なデザイン要素です。直感的に使える体験を実現するには、アフォーダンスとの違いを理解し、ユーザーのメンタルモデルに合ったシグニファイアを設計することが不可欠です。現代の複雑なシステムにおいても、「気づかせる力」を持つシグニファイアは、優れたUXの基盤として今後も重要性を増していくでしょう。
PuzzleEffectではユーザーの誘導体験を専門とするデザイナーが在籍しています。その中でシグニファイアを重視したデザイン設計も行っております。興味が湧いた・話を聞いて見たい方はぜひご連絡・ご相談ください。