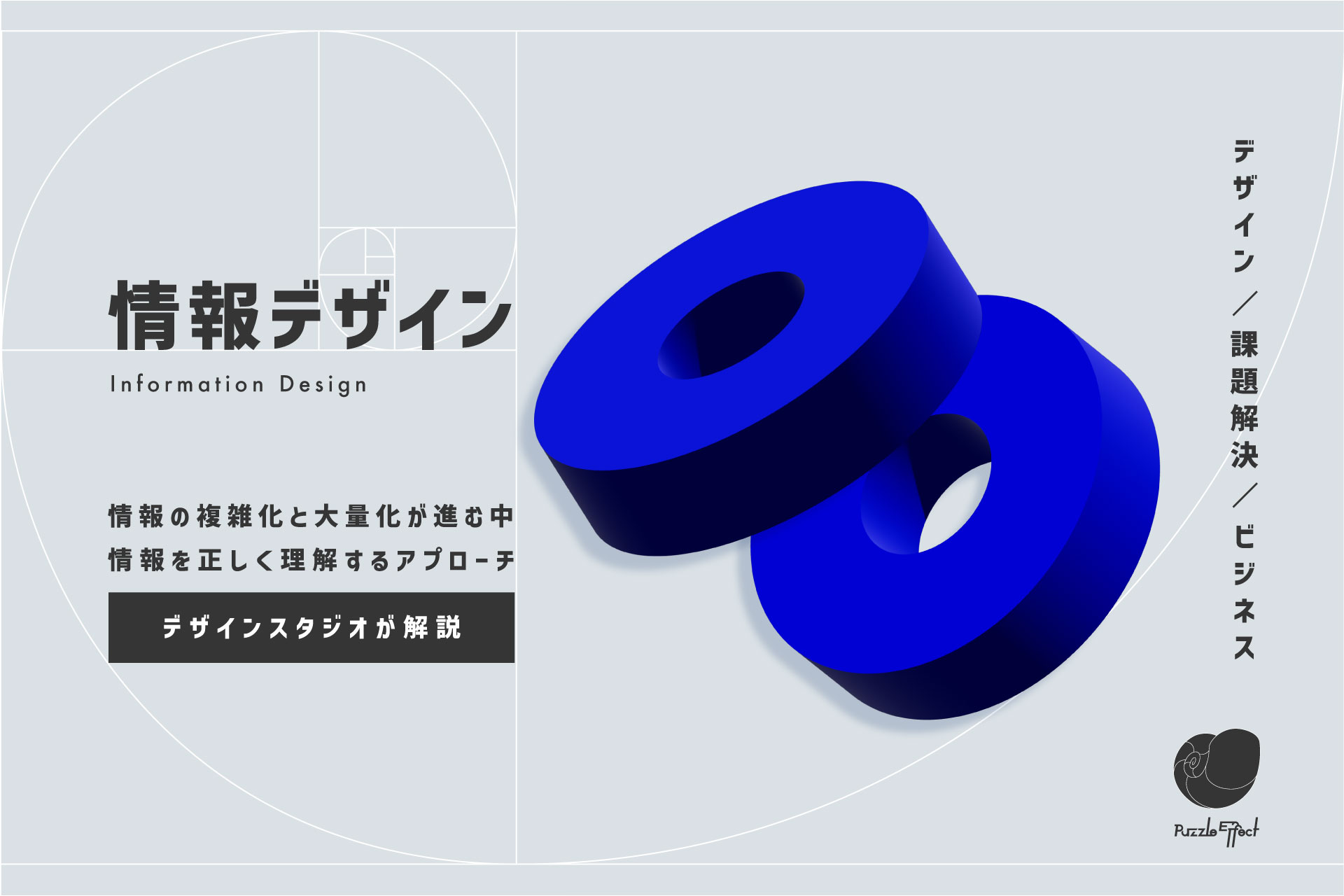情報デザイン(Information Design)とは、情報を分かりやすく、伝わりやすく整理・構成するデザインのことです。文字・図・写真・色・レイアウトなどを適切に組み合わせ、情報の受け手が理解しやすい形にすることを目的とします。ITパスポートや各大学などで注目される情報デザイン、今回の記事では、詳しく解説していきます。
情報デザインとは?情報を伝えやすくするデザインの重要性と具体例
私たちは日常生活の中で、膨大な量の情報に触れています。ニュース記事、看板、マニュアル、ウェブサイト、アプリのインターフェースなど、さまざまな形で情報が提示されます。しかし、それらがすべてわかりやすいとは限りません。
むしろ、情報が複雑で理解しにくいことも多く、誤解や混乱を招くこともあります。 このような問題を解決し、情報をより分かりやすく整理・構成するのが情報デザイン(Information Design)です。
また、AIなどのイノベーションを活用したサービスの開発や、UI/UXデザインやプログラミング、情報科学をも取り入れた新たなデザイン手法と、社会に関わる事柄も情報デザインとされています。
情報を整理し、効果的に伝えるデザイン
例えば、駅の案内板が分かりにくいと、利用者はどこへ行けばよいのか迷ってしまいます。
しかし、文字の大きさや色分け、アイコンやピクトグラムなどの配置が工夫されていれば、一目で行き先が分かります。
このように、情報を伝える手段を最適化し、スムーズに理解できるようにすることが情報デザインの目的です。
情報デザインの目的
情報デザインには、以下のような重要な目的があります。
① 分かりやすさの向上
情報を整理し、受け手が迷わずに理解できるようにします。例えば、長い説明文を簡潔な箇条書きにしたり、視覚的な要素を取り入れたりすることで、情報が頭に入りやすくなります。
② 直感的な理解
言葉だけではなく、図やアイコンを使うことで直感的に理解できるデザインを作ります。例えば、非常口のマークは文字がなくても意味が伝わります。
③ ユーザーの行動をサポート
適切な情報提供により、受け手がスムーズに行動できるようにします。例として、観光地の案内板やショッピングモールのフロアマップなどがあります。
④ 情報の信頼性向上
分かりにくい情報は、誤解やミスを招く可能性があります。情報デザインによって正確な情報を整理し、信頼性を高めることができます。
情報デザインの具体例
情報デザインは、私たちの身近なさまざまな場面で活用されています。以下に代表的な例を紹介します。
① 公共サイン(案内表示)
公共の場では、言葉が通じない人にも情報を伝える必要があります。そのため、シンプルなアイコンや色分け、分かりやすいフォントなどが工夫されています。
② インフォグラフィックス(情報を視覚化した図)
複雑なデータを簡潔に伝えるために、棒グラフ、円グラフ、フローチャートなどが活用されます。プレゼン資料やホワイトペーパーなど、ビジネスの場でも情報デザインは深く関わっています。
③ マニュアル・取扱説明書
言葉だけではなく、イラストや写真を活用することで、ユーザーが正しく理解しやする必要があります。
④ ウェブサイトやアプリのUI/UXデザイン
ウェブサイトやアプリでは、ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるようにデザインされています。
⑤ 地図・路線図
たとえば、東京の地下鉄の路線図はカラフルに色分けされ、各路線の区別がしやすくなっています。複雑な情報を整理し、一目で理解できるようにするのが情報デザインの役割です。
情報デザインの法則①『LATCH』
情報を正しく伝えるためには、その整理方法が重要になります。どんなに価値のある情報でも、適切に整理されていなければ、受け手が理解しづらく、正しく活用できません。そこで、情報デザインにおいて広く用いられるのが、『LATCH』という分類法です。
『LATCH』とは、リチャード・ソール・ワーマン(Richard Saul Wurman)が提唱した、情報を整理・分類するための5つの基本原則です。この5つの頭文字をとったもので、それぞれ以下のような意味を持ちます。
- L (Location) – 場所による分類
- A (Alphabet) – アルファベット順の分類
- T (Time) – 時間順の分類
- C (Category) – カテゴリ別の分類
- H (Hierarchy) – 階層構造の分類
この分類法を用いることで、情報を受け手が理解しやすい形に整理し、素早く必要な情報へたどり着けるようになります。それでは、それぞれの分類方法について詳しく解説していきます。
情報デザインの法則②『アフォーダンスとシグニファイア』
情報を分かりやすく伝えるためには、「どのように使えばよいか」を直感的に理解できるデザインが重要です。その概念として、「アフォーダンス」と「シグニファイア」がよく用いられます。
アフォーダンス(Affordance)とは?
「アフォーダンス」とは、環境や物が持つ「使い方のヒント」を指します。
例えば、ドアノブを見れば「回す」、ボタンを見れば「押す」というように、対象物が持つ形状が自然と動作を誘導するものです。
▶ アフォーダンスの例
- コップの持ち手 → 持ちやすいから自然と握る
- 椅子の形 → 座るためのものだと分かる
アフォーダンスが適切に設計されていれば、説明がなくても使い方が直感的に理解できます。
シグニファイア(Signifier)とは?
シグニファイアは、アフォーダンスをより明確にする「手がかり」のことを指します。
例えば、「ここを押す」と書かれたボタンや、「引く」と書かれたドアのラベルがシグニファイアにあたります。
▶ シグニファイアの例
- ドアに「押す(PUSH)」のラベルがある → 押せば開くと分かる
- スクロールの矢印 → 下に動かせると示す
シグニファイアを適切に設計することで、誤解を防ぎ、ユーザーがスムーズに行動できるようになります。
▶ アフォーダンスとシグニファイアの関係
アフォーダンスだけでは不十分な場合に、シグニファイアを補助的に使うことで、より分かりやすいデザインになります。
例えば、「押して開くドア」なのに取っ手があると、引いてしまうかもしれません。その場合、「PUSH」のラベル(シグニファイア)を加えることで誤解を防ぐ」という考え方です。
まとめ
情報デザインは、伝えたい内容を分かりやすく整理し、受け手に正しく伝えるための重要な手法です。適切なデザインを意識することで、情報の伝達力を高めることができます。